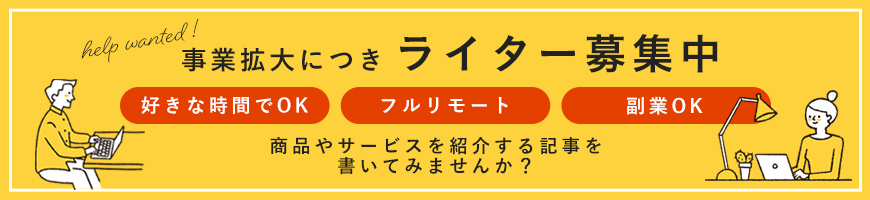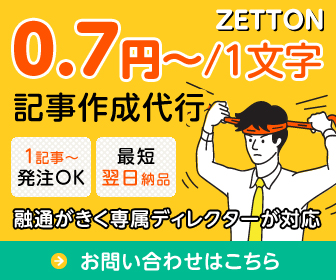インフルエンサーマーケティングを実施したいものの、「どの媒体を利用すべきか」「どのようなメリットがあるのか」など、さまざまな疑問を抱えて立ち止まっている方も多いでしょう。
利用すべき媒体は、宣伝したい商品やそのターゲットなどによって異なります。インフルエンサーマーケティングを行うことで、ユーザーにとって信頼しやすい宣伝を実施することが可能です。
今回の記事では、インフルエンサーマーケティングの概要や適した媒体、メリット・デメリットなどについて解説します。記事を読むことで、インフルエンサーマーケティングを始めやすくなりますよ。
目次
インフルエンサーマーケティングとは

インフルエンサーマーケティングとは、SNSなどで大きな影響力があるインフルエンサーに、自社の商品やサービスを紹介してもらうマーケティング手法のことです。インフルエンサーの力を借りることで、商品やサービスを利用してもらう・自社の認知を広める・自社商品のファンになってもらう、といった効果を期待できます。
インフルエンサーマーケティングは需要が拡大していくと思われる
インフルエンサーマーケティング向けの需要は、今後さらなる高まりを見せることが期待できます。
2023年におけるインフルエンサーマーケティング市場は、およそ741億円(出典:サイバー・バズ/デジタルインファクト調べ)となっています。この数は、前年比の120%にあたる数です。2027年には、2023年の約1.8倍となる1,302億円にまで上ることが予想されています。
インフルエンサーマーケティングを実施する媒体

インフルエンサーマーケティングを実施できる主な媒体としては、以下が挙げられるでしょう。
Instagramとは、画像や動画を主体とした投稿が行えるSNSです。
| 日本での普及率 | 50.1% |
|---|---|
| メインのユーザー世代 | 10〜30代 |
| 特徴 |
・画像や動画がメイン ・拡散性はそこまで高くない ・利用者は女性がやや多いものの、男女どちらも利用している |
インフルエンサー市場の主流は、2018年以降、X(旧Twitter)やFacebookからInstagramへと変わりつつあります。インフルエンサーマーケティングの9割以上は、Instagramで実施されているといわれています。
Instagramは、センスの良い写真や動画が好まれるメディアです。そのため、ブランディングを兼ねたインフルエンサーマーケティングと相性が良い傾向にあります。ファッション・旅行・コスメ・料理など、文章よりも写真や動画の媒体で閲覧することが推奨される商品やサービスは、特に向いているといえるでしょう。
YouTube
YouTubeは、ユーザーが動画を見たり投稿したりできるプラットフォームです。
| 日本での普及率 | 87.1% |
|---|---|
| メインのユーザー世代 | 10〜50代 |
| 特徴 |
・ユーザーの年代が幅広い ・動画のジャンルが豊富 ・スマホやPCのみならずテレビで視聴される機会も増えている |
小さな子ども向けのチャンネルが多いことから、10歳未満の子どもまで利用しているなど、年代の幅広さが特徴的な媒体です。そのため、さまざまな年代に向けた商品やサービスを宣伝できるでしょう。
投稿媒体が動画であることから、テキストでは伝わりにくい内容を伝えたり、魅力的な映像表現によってユーザーを引きつけたりする効果も期待できます。
TikTok
TikTokは、短い動画を見たり投稿したりできるプラットフォームです。
| 日本での普及率 | 28.4% |
|---|---|
| メインのユーザー世代 | 10〜20代 |
| 特徴 |
・縦型動画がメイン ・カジュアルなものが受けやすい |
TikTokはほかの媒体以上に、若い世代の利用者が多い傾向にあります。そのため、ビジネス色の強い投稿は避けられやすいです。TikTokを利用する際は、若い世代に受けやすいカジュアルなコンテンツで攻める必要があるでしょう。
X(旧Twitter)
Xは、短めの文章や画像・動画を投稿できるSNSです。
| 日本での普及率 | 45.3% |
|---|---|
| メインのユーザー世代 | 10〜40代 |
| 特徴 |
・投稿の拡散力が強い ・リアルタイムな情報を見つけやすい ・1投稿につき画像を4枚載せられる |
Xは、リポスト(旧:リツイート)によってユーザーの投稿を拡散できる点が最大の特徴です。ユーザーの印象に残る投稿を行えば、リポスト機能によって爆発的な拡散を期待できます。
1回の投稿に画像を4枚掲載できるため、画像をうまく利用すれば、ひとつの投稿に載せる情報量をより濃いものにできます。
インフルエンサーマーケティングのメリット

インフルエンサーマーケティングには、以下のようにさまざまなメリットが存在します。
➀アクティブ率が高いSNSは広告効果が高い
SNSはアクティブ率が高いコンテンツであり、今やほとんどの人がSNSを利用しています。対してテレビや新聞は、年々ユーザーが少なくなりつつあります。
したがって、ユーザーが減少傾向にあるテレビや新聞で宣伝を行うよりも、多くのユーザーが利用するSNSで広告を出した方が、多くの人の目に留まりやすいといえるのです。
➁ユーザーが使用感をイメージしやすい
インフルエンサーは本来企業とは関係のない人物であるため、企業側ではなく消費者側に立った商品・サービスの感想を伝えてくれます。消費者の視点で感想を伝えることで、ユーザーにとって共感性が高く、使用感をよりイメージしやすい宣伝になるでしょう。
➂比較的安価に行える
費用についてはのちほども紹介しますが、インフルエンサーマーケティングは従来のさまざまなマーケティング手法に比べ、比較的安価に行いやすいところがメリットです。特にテレビCMなどのテレビ広告と比較すると、費用は安いです。
安価に行えるため、気軽に始めやすい点もインフルエンサーマーケティングのメリットといえるでしょう。
④特定のユーザーに訴求できる
インフルエンサーマーケティングは、特定の年代や性別、趣味を持つユーザーに対して訴求します。
たとえば、女性のコスメについて発信するインフルエンサーをフォローしている主なユーザーは、コスメや美容に関心の強い女性です。コスメや美容に関する商品・サービスを訴求したいのであれば、宣伝を任せるのにうってつけな人物といえるでしょう。
特定のターゲットに対して訴求できるところが、インフルエンサーマーケティングの大きなメリットです。
⑤投稿が拡散される可能性もある
SNSの中には、Xなどのようにユーザーの投稿が拡散される機能を持ったものも存在します。この拡散性を利用すれば、さらに幅広いユーザーへ宣伝できる可能性が高いです。特にインフルエンサーの投稿は、企業の投稿よりも信頼性や共感性が高いため、ユーザーが安心して拡散されやすいです。
⑥ブランディング効果が期待できる
たとえば料理に関する発信をしているインフルエンサーであれば、フォロワーから「料理に関してはこの人が全面的に信用できる」と思われているケースがほとんどです。このようにインフルエンサーのほとんどは、そのユーザーが発信している分野に関して高い信頼性があります。
大きな信頼を獲得しているインフルエンサーが自社に関する投稿を行えば、「この商品やサービスは信頼できそう」と思ってもらいやすく、ポジティブなブランドイメージを持ってもらえる効果を期待できます。
⑦「広告らしさ」を感じにくく信頼されやすい
企業が制作した広告は、どうしても広告らしさが出てしまいます。そのため、内容をしっかり見る前に「広告だから」とスキップされたり、アドブロック機能でブロックされたりするケースも珍しくありません。
対してインフルエンサーマーケティングは、企業側の人間ではないインフルエンサーが宣伝を行います。インフルエンサーが自身のカラーにマッチした宣伝を行ってくれるため、広告らしさを感じにくく、比較的安心して見てもらえます。
宣伝はインフルエンサーの通常の投稿によって行われるため、アドブロックで弾かれることもなく、ユーザーに届けられるのです。
インフルエンサーマーケティングのデメリット

さまざまなメリットを持つインフルエンサーマーケティングですが、注意すべきポイントもあります。
➀炎上のリスクがある
SNSに投稿を行うときに最も注意すべき要素のひとつが、炎上です。近年では時代にそぐわない投稿や配慮に欠けた投稿を行うと、すぐに炎上してしまいます。
企業が炎上すると、今までに得た信用を一度で大きく失うことになります。インフルエンサーマーケティングを行う際は、現代にマッチした価値観とリテラシーを持って対応し、炎上を引き起こさない投稿となるよう細心の注意を払いましょう。
➁ステルスマーケティングは行政処分の対象になる
ステルスマーケティング(ステマ)とは、企業に報酬をもらって宣伝を行っているにもかかわらず、それを隠して宣伝することです。「たまたま使ったこの商品がすごく良かった」という形で、あたかも自分が偶然その商品を利用したかのように投稿を行うことが該当します。
ステルスマーケティングはユーザーを騙す行為にあたるため、炎上する可能性があります。ステルスマーケティングを行った場合、今後は依頼主が行政処分の対象となることが決定しました。ステルスマーケティングはユーザーからの信頼を大きく失うことにつながるため、避けなければいけません。
➂景表法違反のリスクがある
インフルエンサーマーケティングはやり方を間違えると、景表法に違反するリスクがあります。景表法(景品表示法)とは、商品やサービスの価格や内容、品質等を偽って表示することを規制する法律です。
たとえば、景表法では他社のものよりも優れているわけではないにもかかわらず、自社商品の方が優れていると偽って宣伝すること(優良誤認表示)が規制されています。そのため、インフルエンサーが「A社の商品はB社のよりも使いやすい」といった宣伝投稿を行うと、優良誤認表示にあたる可能性があるのです。
そのほか、競合他社の商品やサービスより特に安いわけではないにもかかわらず、著しく安価であるかのように宣伝すること(有利誤認表示)も規制されています。他社と値段はそこまで変わらないにも関わらず、インフルエンサーが「A社の商品はどこよりも安いよ」と宣伝すると、有利誤認表示に該当します。
④発信内容をコントロールできない
インフルエンサーマーケティングは、企業とは関係のない他者に宣伝を依頼するという手法なので、発信内容をコントロールできないところはデメリットです。事前に丁寧な打ち合わせをしておかないと、企業が宣伝したいイメージとは違う形で宣伝される可能性があります。
意図しない形で発信が行われれば、自社ブランドのイメージが崩れたり、良い成果が出にくくなったりする原因になるかもしれません。
⑤インフルエンサーの選定にはコストがかかる
どのインフルエンサーに任せるのかを考えるのは、簡単ではありません。インフルエンサーの選択を誤ると、大きな効果が見込めなかったり、炎上につながったりするリスクもあります。
多くの人に届けるために、フォロワー数で決めようと考えている方も多いでしょう。しかし、フォロワーの数だけで決めるのはうまいやり方とはいえません。
現代ではフォロワーをお金で購入できるので、フォロワーの数がインフルエンサーの実力に伴っていない可能性があります。さらに、いくらフォロワーがいても、そのフォロワーが自社商品のカラーと合っていなければユーザーの購買にはつながりません。
インフルエンサーマーケティングを行う際は、目指したいゴールを見据え、それにマッチしたインフルエンサーを選定する必要があります。インフルエンサーを選定する上でチェックしておきたい項目は、以下のとおりです。
- インフルエンサーが行う投稿の質
- インフルエンサーとそのフォロワーはどのような関係にあるのか
- 自社商品やサービスとインフルエンサーに親和性があるか
- インフルエンサーが過去に行った宣伝投稿はどういった内容か
- 過去に行った宣伝の投稿に大きな反応はあったのか
- インフルエンサーが行っている投稿はフォロワーからしっかりと反応をもらっているか
- インフルエンサーのフォロワーはどのような性別・年代・趣味のユーザーなのか
インフルエンサーマーケティングにかかる費用

インフルエンサーマーケティングにかかる費用は、1フォロワーあたり3〜8円程度が相場とされています。1フォロワーにつき5円と仮定すると、50,000人のフォロワーを持つTikTokerであれば、50,000人×5円で1投稿あたり25万円ほどかかることになるでしょう。
実際は、広告代理店やインフルエンサーマーケティングの会社に払う費用がここに加わるので、10〜30%ほど追加の費用がかかることが多いです。具体的な費用について知りたい方は、広告代理店やインフルエンサーマーケティング会社に見積もりをとりましょう。
インフルエンサーマーケティングのKPI

KPIとは、会社が決めたゴールに向けて達成すべき目標数値のことです。ゴールまでの過程における、中間目標のようなイメージです。具体的には、「チャンネル登録者数を2,000増やす」「フォロワーを500増やす」といったものが挙げられます。
インフルエンサーマーケティングを行う際は、ゴールに合わせて適切なKPIを設定しましょう。ここからは、以下の媒体を利用した際の、KPIの例について解説します。
InstagramのKPI
InstagramのKPIは、以下のような項目を利用して決めることが推奨されています。
- 宣伝投稿の閲覧数
- いいね!やコメントをもらった数
- 増えたフォロワーの数
- 検索エンジンにおける検索数の増加量
- ハッシュタグ投稿数の増加量
YouTubeのKPI
YouTubeで実施するマーケティングのKPIは、以下の項目を利用して決めるとよいでしょう。
- 動画が再生された回数
- 高評価の数
- 自社のチャンネル登録者の増加量
- コメントの数
- 動画を再生したユーザーの人数
- 宣伝動画がユーザーの画面に表示された数
- 宣伝動画のサムネイルを閲覧した人のうち、動画を再生したユーザーの数
TikTokのKPI
TikTokであれば、以下のような項目を利用して決めることが推奨されています。
- 動画の再生回数
- フォロワーの増加量
- 動画の再生時間
- プロフィールが表示された数
- コメントの数
- シェアされた数
- 動画の平均視聴時間
X(旧Twitter)のKPI
Xで実施するマーケティングのKPIは、以下の項目を利用して決めましょう。
- ユーザーがポストを閲覧した数
- ポストを通して、自社のプロフィールに到達したユーザーの数
- 宣伝投稿によって増えた、自社のフォロワー数
まとめ
今回の記事でご紹介してきたように、インフルエンサーマーケティングには、特定のユーザーに訴求できたり広告らしさを感じにくかったりと、さまざまなメリットがあります。しかし、炎上リスクがあったり、ステマにあたる可能性があったりと、注意すべきポイントも存在します。
実際にインフルエンサーマーケティングを行うときは、自社に適した信頼できるインフルエンサーを慎重に選定しなければなりません。インフルエンサーマーケティングを行っている代理店に依頼することも可能ですが、その場合は追加の費用がかかります。
インフルエンサーマーケティングで得たいゴールを達成するためには、明確なKPIを決めておくことが大切です。それぞれの媒体に合ったKPIを定めておくことで、インフルエンサーマーケティングを有効に活用できるでしょう。
この記事を参考に、自社に合ったインフルエンサーマーケティングを行ってみてくださいね。