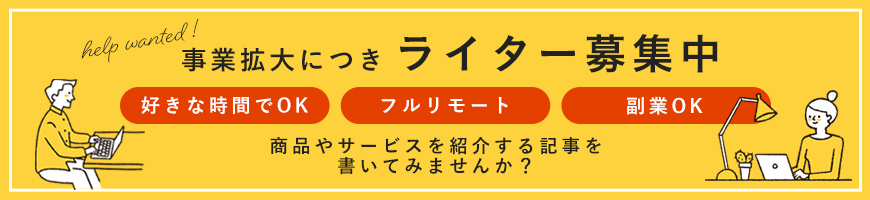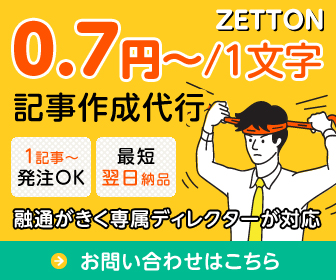自社サイトの運営を任されたときに「どうやって集客すればいい?」「コンテンツはどうすれば…」と、疑問や不安を感じていませんか。このようなときは、まずSEOライティングについての知識を深めていきましょう。
今回は、SEOライティングの進め方や重要な考え方、必要な要素について解説します。SEOライティングは、Webページの運営を支える根幹的な手段です。
基本的な知識を頭に入れることで、サイト運営のコツやテクニック習得につなげられるだけでなく、自社の利益獲得も期待できます。会社の期待に応え、Web担当者としての力を発揮するためにも、Webライティングの基本を身につけましょう。
目次
SEOライティングとは

SEOライティングとは、Webの検索結果でサイトの上位表示を目指すためのライティング方法です。日本において、検索エンジンのトップシェアはGoogleです。つまり、SEOライティングでは、Googleの評価基準を満たすライティングを行い、検査結果の上位表示を目指す必要があります。
Googleの評価基準では、ユーザーの利便性(ユーザーファースト)が重要視されています。SEOライティングにおいても、ユーザーニーズを満たす文章を執筆・掲載しなければ、価値あるコンテンツと評価されません。
もちろん、評価の軸はほかにも複数あるため、包括的な知識を身につけ、検索エンジンへの対策を行いましょう。
SEOライティングをすべき理由

SEOライティングをすべき理由について、ユーザー・企業それぞれの視点で解説します。
ユーザーの悩みを解決しやすくなる
SEOライティングを意識すると、Webページ(記事)の質が上がり、ユーザーの悩みを解決に導けます。前述したとおり、Googleはユーザーの利便性を重要視しています。
Googleの検索エンジンに評価されるには、ユーザーの検索意図(潜在ニーズ)に適した回答を提示していることが重要です。つまり、検索結果の上位に表示されるような記事を作成することで、自ずとユーザーの悩みを解決しやすくなります。
文章が分かりやすいので、一度読めば理解できる
SEOライティングによって書かれた文章はユーザーにとって分かりやすく、一度読めば理解できるWebページとして認知されます。SEOライティングを実施する目的は、商品購入やサービス利用、自社ブランドの認知拡大などのコンバージョン(最終的な成果)達成です。ユーザーを集めることだけを目的としているわけではないので、自社サイトに流入したユーザーを誘導する必要があります。
誘導にあたって重要なのは、ユーザーを安易にページから離脱させないことです。例えば、専門知識を持たないユーザーに対し、専門用語を羅列した文章は読みにくいので、すぐにページから離脱してしまうでしょう。
「ユーザーが離脱しにくい記事を制作する」ということは、ユーザーにとって分かりやすく、一度読めば理解できるWebページとして認知されることにつながります。
流入数が伸びるので、お問い合わせや資料請求数が増加する
SEOライティングにより検索結果の上位に表示されれば、問い合わせや資料請求数が増加し、自社の売上にもポジティブな影響をもたらすでしょう。SEOライティングによる流入数アップは、以下のようなメリットがあります。
- 質の高いユーザーを集められる
- 中長期的に顧客獲得のチャンスを得られる
- 自社ブランドやサービスのブランディング(ユーザーに価値を認めてもらう)につながる
SEOライティングでは、特定のジャンルに応じたキーワードを設定することで、そのキーワードで検索するユーザーを集めることが可能です。そのため、自社商品・サービスへの需要が高いユーザーを集めやすく、問い合わせや資料請求などにもつながります。
制作した記事は削除しない限りそのまま残り続けるため、中長期的な集客が可能です。したがって、顧客獲得のチャンスを広がるだけでなく、自社のブランディング効果も見込めます。
SEOライティングをするうえで重要な考え方

SEOライティングを始める際は、次項で解説する考え方も頭に入れておいてください。SEOライティングにおける基礎的なポイントばかりなので、理解しないまま始めてしまうと期待する効果を得られない恐れがあります。
検索順位1位を目標にする
SEOライティングは、検索順位で1位になることを目標にして始めましょう。アメリカの「Advanced Web Ranking社」のデータ(2023年12月時点)によると、検索結果1位の平均クリック率は約46%なのに対し、2位は約10%まで落ち込んでいます。つまり、多くのユーザーが検索結果1位の記事に注目・信頼し、アクセスしていることが分かります。
必ずしも検索結果1位にこだわる必要はありませんが、下位に表示されるほどユーザーの流入・認知は期待できません。問い合わせ数アップや商品・サービスの購入などを目標に掲げる場合、検索結果1位を目指してSEOライティングを始めることが大切です。
検索ユーザーのニーズを読み解く
検索ユーザーのニーズ(検索意図)を読み解くことで、検索順位アップを期待できます。検索意図とは、ユーザーが検索する目的や背景です。
例えば、ダイエット方法を検索するユーザーの場合、「夏は海で遊びたい」「病気を予防したい」などの潜在的なニーズが隠れています。キーワードによって検索意図は異なるため、事前に上位記事の傾向やサジェスト(検索候補)・関連キーワードを確認することで、検索意図を読み取ることが可能です。
ユーザーニーズが満たせる記事は、ユーザーファーストなWebページとして検索エンジンから評価されやすくなり、検索順位アップへつながります。
嘘偽りのない正しい情報を提供する
嘘偽りない正しい情報を提供することで、企業としての信頼はもちろん、検索エンジンの評価にもポジティブな影響を与えます。企業が運営するWebサイトは情報発信者としての責任が大きく、閲覧するユーザーも「企業だから安心」という理由で信用します。
誤った情報でユーザーに被害を与えないためにも、専門家へのインタビューや監修者を付けるなど情報の精度を高めましょう。特に専門性の高いジャンル(法律や医療関係)は、情報に誤りがあると身体的・金銭的な損失をユーザーに与える可能性があるので、特に注意が必要です。
インタビューや監修は、検索エンジンにおける評価指標の1つ「権威性」に対して、ポジティブな評価を得られます。正しい情報を発信し、検索順位アップとユーザーからの信頼を獲得しましょう。
定期的なリライトで記事の質を高める
定期的なリライトで記事の質を高め、検索エンジンの評価を高めることを意識しましょう。リライトとは、リリース済みの記事を改善・再構築することです。例えば、タイトル・見出しの最適化や情報の更新などが挙げられます。
リライトを行うと、記事を新しく制作する手間を省き、低評価の要因となる「コンテンツの重複」が発生しにくくなります。さらに、ユーザーへ最新情報を提供できるので、間違った情報を発信するリスクも軽減するでしょう。
このように、コストを抑えて記事の質の向上を狙えますので、SEOライティングを始める際は定期的なリライトも行ってみてください。
記事のフィードバック(効果測定)を行う
定期的に記事のフィードバック(効果測定)を行い、測定結果から改善の方法や方向性などを検討することも大切です。フィードバックでは、以下の項目で記事の反響を測定します。
- PV数(閲覧数):各ページのPV数は期待する数値なのか
- 検索順位:指定したキーワードで上位表示できているか
- CV(コンバージョン)率:目標とする成果(問い合わせや商品購入など)が達成できているか
- 直帰率:アクセスしたユーザーが、何のアクションも起こさずに離脱していないか
- 滞在時間:各ページでユーザーがどのくらい滞在しているか
- 被リンク:他のWebサイトに、自社サイトのリンクが貼られているか
PV数や検索順位は、記事の質が保たれているか、リライトすべきかを判断する材料になります。ただし、これらの数値は、あくまでもコンバージョン達成への導線が適切かを判断するための指標です。必ずCV率もチェックして、成果を得られる施策が講じられているか確認しましょう。
直帰率・滞在時間は、ユーザーの興味・関心の度合いを確認する指標です。直帰率が低く、滞在時間が長いほどページの質がよく、ユーザーニーズを満たせている可能性が高いです。
また、自社と関連性の高い被リンクは、検索エンジンから好評価を得やすくなります。ただし、被リンクの購入や過剰な相互リンクはペナルティの対象となり、評価を著しく下げる恐れがあるので注意しましょう。
これらのフィードバックを定期的に確認しておくことで、SEOライティングによる施策が適切か判断できます。
SEOライティングに必要な要素

SEOライティングに必要な要素を8つ紹介します。効果的なSEOライティングを実践するために必要な基本事項なので、必ず目を通してください。
①タイトル
タイトルは、ユーザーが検索結果を閲覧した際に、アクセスすべきページかどうか判断する重要なポイントです。そのため、ユーザーニーズを満たす文言を検討し、タイトルを決めなくてはいけません。
タイトルを設定する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
- タイトル文字数は30文字を目安に設定(検索結果にタイトル全文が表示されやすい)
- 上位表示を狙うキーワードをタイトルに含める
- ほかのページと類似するキーワードは含めない
- キーワードは自然な形で入れる(文字の羅列にならない)
- キーワードはなるべくタイトルの先頭に入れる
- ターゲットユーザーが誰か明確にする
- クリックしたくなるフレーズを入れる
検索結果に表示されやすいよう、検索対象となるキーワードは必ずタイトルに含めてください。タイトルの前方にキーワードを入れ込むと、ユーザーの目に留まりやすくなります。
注意点として、タイトルと記事内容にギャップがあると、ユーザーはすぐ離脱する恐れがあります。ユーザーファーストを念頭に、タイトルと記事内容は必ず一致させましょう。
②ディスクリプション
ディスクリプション(メタディスクリプション)とは、記事内容を要約した100文字程度のテキストです。検索結果ではタイトル下に表示され、ページ内にユーザーの求める情報が含まれているのか判断される箇所です。
ディスクリプションの表示方法には、以下の2つの方法があります。
- ユーザーの検索キーワードに関連した内容をページ内から自動的に抜粋
- 運営者が設定した内容を表示(ページ内容を正確に説明していると判定された場合のみ)
ディスクリプションは運営者が自ら設定できますが、内容によっては自動的に抜粋される文章が優先されるので注意してください。どうしてもユーザーに伝えたい内容がある場合は、以下のポイントを押さえてディスクリプションを作成しましょう。
- 100文字程度の簡潔な内容に抑える
- 誰に向けた内容なのかを明確にする
- ページを読むメリットを伝える
- 具体的な内容を含める
ユーザーをページに誘導するためには、ディスクリプションの質にもこだわる必要があります。
③リード文(冒頭文)
リード文とは、タイトルと本文(もしくは目次)の間に記載される、記事の要約文を指します。ユーザーにとっては、欲しい情報の有無や閲覧するメリットなどが把握できる文章です。
記事を読み進めてもらうために、以下のポイントを押さえてリード文を作成しましょう。
- 誰に向けた、何の記事なのか、何が解決できるのかを明確にする
- 記事の要点を押さえた内容を記載する
- ユーザーへのメリット、読むべき理由を伝える
書く内容や書き方に迷ったときは、上位表示されるページのリード文を参考にしてみてください。
④見出し・構成要素
見出しや構成要素は、ユーザーがアクセスした際に、本文内に何が書かれているか把握してもらう役割があります。このまま読み進めるべきかの判断に使われるため、以下のポイントを押さえて、見出しと構成を設置しましょう。
- ユーザーの可読性を考慮して、見出しを多く設置しすぎない
- 見出しの一文はシンプルかつコンパクトにする
- 対象となるキーワードを見出しに含める
- ターゲットユーザーの属性に合わせた単語を使用する
見出しの文字数に制限はないものの、ユーザーが内容を把握しやすいようシンプルな文面を意識してください。さらに、ユーザーの属性に合わせた単語を使用することで、より内容が伝わりやすくなります。
例えば、メールの書き方に関する記事の場合、「メールが遅れる」と「メールの遅延」で、どちらの単語がターゲットユーザーに伝わりやすいのかを検討することが重要です。
見出しや構成要素の設定は記事の質にもかかわる重要な部分なので、時間をかけてでも十分に検討する必要があります。
⑤本文
本文はユーザーの悩み・課題を解決する重要な要素です。ただし、ダラダラと執筆しても読み進めてもらえないため、本文を執筆する際は以下のポイントを押さえましょう。
- 冗長表現はNG(~することができる、~があるものである、など)
- 一文一義(1つの文章に1つの情報)を意識する
- 同じ語尾の連続は控える
- 誤字脱字や二重表現(元旦の朝、まずはじめに、など)はNG
冗長表現や同じ語尾の連続は、ユーザーに稚拙な印象を与えます。さらに、一文一義ではない文章も読みにくさの原因となるため、本文を執筆した際は音読しながら読みやすさを確認しましょう。これらを踏まえ、NGな表現・OKな表現を紹介します。
SEO対策は、運営者にとって集客・売上の効果に期待できる重要な業務なので、担当者は専門的な知識を必要とするのはもちろんですが、知識だけ持っていても実務で使えなければ意味がないです。有効活用することができるようになるためにも、実際に手を動かして知識をアウトプットすることが重要です。
<OKな表現>
SEO対策は、集客・売上にもつながる重要なWeb業務です。担当者は専門知識を頭に入れ、アウトプットしながら実践的なスキルも身につけましょう。
ユーザーに読み進めてもらえるよう、細かい箇所まで配慮して執筆を進めましょう。
⑥表やリスト、画像
文章内の要点は、表やリスト、画像などを使うと伝わりやすくなります。文章だけが書かれたページは読みにくいだけでなく、ユーザーが疲れてしまいます。
例えば、以下のように表・リストを活用しましょう。
- 複数行の文章は箇条書きにする
- いくつかのパターンにわかれる場合は表を使う(項目別の料金やメリット・デメリットなどの説明)
箸休めのような要素として表・リストなどを組み込むだけでも、ユーザーの集中力を保ち、読み進めてもらいやすくなります。
⑦引用
信ぴょう性のある情報を伝える場合、引用も活用してください。引用とは、情報源となるページから文章をそのまま挿入することです。ただし、文科省によると、引用には以下の条件が提示されています。
2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)
3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)
4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)
引用:文化庁 令和5年度著作権テキスト
つまり、引用を用いる際は、必然性があり、引用した出所は必ず明示しなければなりません。さらに、自社の記事を主体として、引用部分が多くなることもNGです。これらを踏まえたうえで、引用により記事の信ぴょう性をアップさせましょう。
⑧執筆者や監修者の情報
専門的な内容を発信する際は、執筆・監修を依頼して誤った情報をユーザーに伝えないよう注意しましょう。「嘘偽りのない正しい情報を提供する」でも解説したとおり、医療や法律など専門的な分野において、誤った情報はユーザーに損害を与えかねません。
正しい知識を提供するためにも、専門家への執筆・監修依頼も検討してください。執筆者・監修者の情報を掲載することで、記事全体に説得力を持たせられます。ユーザーは安心して記事を参考にできるほか、実生活におけるベネフィットも提供できるでしょう。
SEOの観点からも、検索エンジンに信頼性のある記事として評価されやすくなります。上位表示に期待できるので、執筆者・監修者情報の掲載は積極的に行いましょう。
SEO記事で上位獲得できるライティングの進め方とポイント

SEO記事で検索上位を獲得するため、ライティングの進め方とポイントについて順を追って解説します。
STEP1. 目的と課題を改めて確認する
SEOライティングの目的や社内の課題を改めて確認し、今後の方向性を明確にします。方向性とは、どの媒体を使って、どのように目的・課題を達成するか、という点です。
媒体にはいくつか種類があるので、どの媒体が自社にマッチするかチェックしてみましょう。
- コーポレートサイト:自社の概要や商品・サービスなどを紹介する
- サービスサイト:商品やサービス、事業などに関連する情報を掲載する
- ECサイト:商品やサービスの売買を目的としている
- メディアサイト:記事からの流入を目的としている
- SNS:自社アカウントを運用し、ファンとなるユーザーを獲得する
例えば、「集客力が落ちてきている」「売上が伸びない」といった課題の場合、メディアサイトやSNS、サービスサイトなどの活用が有効です。メディアサイト・SNSからユーザーを獲得しサービスサイトへ誘導することで、集客力・売上などの課題解決に期待できます。
まずは目的・課題を明確にして、方向性や媒体を検討しましょう。
STEP2. ペルソナ(ターゲット)を設定する
ペルソナの設定とは、どのようなユーザーにアプローチするのかを決める工程です。ユーザーの属性(年齢や仕事、居住地など)によって抱える悩みや課題が異なります。
SEOライティングでは、ユーザーニーズを満たす記事を掲載しなければならないため、ペルソナを設定しないことには記事を制作できません。自社の事業と照らし合わせながら、どのようなユーザーにアプローチすべきか検討しましょう。
STEP3. ペルソナの行動を予測したうえでキーワードを選定する
ペルソナの行動を予測したうえで、検索しそうなキーワードを選定します。キーワードは主に以下の2種類を選定してください。
- サイトの柱となるキーワード
- 柱に付随する、複合的なキーワード
例えば、ダイエット食品を扱う企業であれば、柱となるキーワードは「ダイエット」です。次に、複合的なキーワードとして、「メニュー」「方法」「女性」などが挙げられます。
ユーザーが目的を持って検索する場合、「ダイエット メニュー」など、2つ以上のキーワードを設定するケースも多いです。そのため、上記のように柱と複合的なキーワードを設定して、記事を執筆しましょう。
STEP4. 記事全体が分かる骨組みを作成⇒ライティングを行う
選定したキーワードをベースに記事全体の骨組みを作成し、ライティングを始めましょう。骨組みとは、記事に盛り込む内容やタイトル、見出しなどです。
ユーザーニーズを満たす骨組みを作成するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 競合調査を行い、どのような内容が盛り込まれているのかチェックする
- ユーザーの検索意図を考慮しつつ、記事に含める情報を整理する
- キーワードを含むタイトルと見出しを作成する
- 共起語が含まれるように調整する
競合調査を行うことで、見出しの内容や配置、盛り込むべき情報を参考にできます。ただし、コピーコンテンツは検索エンジンからペナルティを受ける恐れがありますので、必ずオリジナルの見出しを作成するよう心がけてください。
記事全体に共起語が含まれていると、検索エンジンから「ユーザーニーズに応えている」と判断されやすくなります。共起語とは、特定のキーワードと一緒に使用されやすい言葉です。不自然にならない程度に共起語を盛り込み、検索順位のアップを狙いましょう。
STEP5. 定期的なフィードバックとリライトを実施する
「SEOライティングをするうえで重要な考え方」で解説したとおり、定期的なフィードバックとリライトで記事の質を保ちましょう。情報は流動性があり、常に最新の状態に保たなければ誤った内容を発信する恐れがあります。
また、フィードバックを行うことで、「コンバージョンに至っていない」「ユーザーニーズを満たせていない」などの問題点を見つけられます。新規記事作成よりも低コストでSEO対策ができるため、定期的なフィードバックとリライトは欠かせない工程です。
SEOライティングをするうえで注意すべき3つのこと

SEOライティングをするうえで注意すべき3つのポイントを解説します。
誤字脱字や表記ゆれに注意する
誤字脱字や表記ゆれは、文章が読みにくくなるほか、SEOの観点からも注意すべきです。どちらも些細なミスかもしれませんが、気になったユーザーにとってはストレスとなり、早期離脱につながります。さらに、対策したいキーワードを間違って表記していた場合、検索エンジンに評価されない可能性があります。
誤字脱字・表記ゆれの対策方法を見ていきましょう。
- 表記ルールを策定しておく
- 時間をおいてから読み返す
- リリース前には第三者によるチェックを入れる
- 校正ツールを使用する
表記ルールを決める際は、間違えやすい言葉や頻出する言葉をピックアップして、各言葉の表記方法を決めておきましょう。チェックの際も見逃すリスクが減少し、記事の質をアップさせられます。
また、校正ツールを利用すれば、最終チェックの効率と精度が上がります。MicrosoftのWordには校正機能が搭載されているので、社内に専用ツールがない場合は利用してみてください。
外部サイトの文章を剽窃(ひょうせつ)しない
外部サイトの文章を剽窃(ひょうせつ)した場合、検索エンジンにコピーコンテンツとして判断され、検索順位を落としかねません。剽窃とは、外部のコンテンツを盗み、自分のオリジナルとして発信する行為です。「外部サイトをそのまま流用している」「記事の全文をコピーしている」など、無断で複製された記事はペナルティの対象になるので注意しましょう。
また、文章の剽窃は、著作権侵害で訴えられる恐れがあります。企業として信頼を損ねてしまえば、ブランドイメージの低下のみならず、顧客離れなど深刻な事態に陥るリスクも否めません。
SEOライティングでは、オリジナルコンテンツを意識した文章を作成し、リリース直前にはコピーコンテンツになっていないか、必ずチェックしてください。無料のチェックツールもありますので、積極的に利用しましょう。
無効のリンクがないかどうか確認する
無効なリンクがないか確認し、ユーザーの離脱や検索エンジンからの低評価などを防ぎましょう。無効のリンクとは、「リンク先のページが削除・移動される」「リンク先で障害が起きている」などが原因で、リンクをクリックしても移動できない状態です。
無効のリンクによるデメリットには以下のようなものがあります。
- ユーザーが期待する情報を得られず、ページを離脱する
- 検索エンジンのクローラー(Webサイトの情報を収集するロボット)が巡回できなくなり、サイト品質の低下を疑われる
上記のような事態に陥らないためにも、無料のチェックツールなどを使い、無効のリンクがないか定期的に確認してください。
まとめ
SEOライティングは、自社の顧客ではないユーザーを集客し、問い合わせ数アップや商品・サービスの購入につなげられる手段です。通常の広告・広報活動よりも低コストで始められるため、集客や売上に課題を抱える企業は積極的に活用しましょう。
「SEOライティングに必要な要素」を参考に、いくつか記事を仕上げてみてください。最初は期待する効果を得られないかもしれませんが、定期的なフィードバックにより記事の質が向上します。
大切なのはユーザーファーストを忘れないことです。自社で抱える課題・問題を解決するためにも、ユーザーのためのサイト運営を心がけましょう。